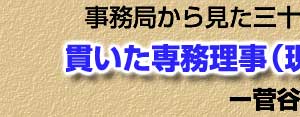 |
 |
吉 野 泰 通
私が東京都中小企業団体中央会(以下中央会という)の前身、東京都商工協同組合連合会(以下連合会という)に昭和二十六年四月就職してから既に三十五年の歳月が流れた。今回「東京都中小企業団体中央会三十年史」の編集に際して、正史としての三十年史とは別個に、事務局の立場から見た中央会三十年を綴ってみてはどうか、との話が大和四郎記念事業企画委員長(現副会長)からあった。
もとより私はその任にないことを考えて、これを固辞したが、「創立以来の事務局職員は君が只一人だ、最古参の君が書かないで誰が書くのだ」との強い言葉に止むを得ず、己の非才を顧りみず、筆をとった次第である。
そこで、私は中央会の事務局史とは何か、何に焦点を当てるべきかについて想いを巡らした。その結果、中央会創立者の一人であり、かつ長期にわたって事務局の陣頭を指揮して来たミスター中央会こと菅谷現会長の“菅谷語録”を紹介し、それが創立間もないころから今日に至るまで、事務局に影響を与え、かつ、リードして来たかを紹介することがもっともふさわしいと考えるに至った。
なお“菅谷語録”は私が勝手に名付けた言葉である。要は、菅谷会長の主として専務理事時代に事務局を指導するための理念を述べたものと理解している。また、一つの経営哲学とも言える。それを今やポピュラーな言葉となった“語録”という表現に置き換えたのに過ぎない。
さて、私ごとで僭越であるが、この三十五年間、職務を通じて多くの人々と知り合い、忠告されたり、助けられたり、今日まで大きな落度もなく、職務に精励してきた。
なかでも私の人間形成のうえで、職業人として厳格に一人前に育ててくれた人が菅谷会長である。私と菅谷会長との出会いは、中央会の前身団体である連合会に就職した時に始まる。
当時、菅谷会長は連合会設立の母体となった東京都中小企業金融懇話会(以下金融懇話会という)の会長をしていた。金融懇話会は商工組合中央金庫(以下商工中金という)の融資利用組合三百余で組織し、商工中金の資金源拡大と、中小企業の組織金融難を打開するために活動していた。このため日夜、政府、国会、都議会に対し、東京都の公金の商工中金への預託、商工債権の消化協力などの陳情、請願の猛運動を展開し、指導者として猛烈な闘志をもって華々しく活躍されていた時で、全国の中小企業界に菅谷頼道ここにありと、すでに頼(雷)名を轟かし、実効をあげていた。
|
その後、連合会が設立されるや、長老で先輩の塩澤達三(初代中央会会長)が会長に、自分は筆頭副会長として塩澤会長の職務代理代行の重責を果たしていた。
あのころ、中小企業運動の指導者といえば、年代は五十代から六十代の人達が圧倒的多い中で、菅谷会長は弱冠三十代の若さ、行動力抜群の男盛りでもあった。 私は未だ二十代の青二才、若さだけが取り柄で、善きにつけ、悪しきにつけ、上司先輩の行動を見習いながら連合会の事務局で、日々を過ごしていた。 当時の日本経済は不況、金融難など極めて悪条件のもとにあって、特に、中小企業の経営環境は厳しく、未曾有の危機を訴える声が東京を初め、全国各地で高まっていた。 こうした中小企業の危機を打開する一つの方途として「組合を組織して商工中金より資金を借入れること」すなわち、中小企業等協同組合法に基づく組合が続々と結成されて、組織金融事業が円滑に運ぶことを目指したものが多かった。つまり、反面、目的が完了すると休眠組合や弱体組合となって、これが全国的に目立って増えてきた時期である。 |
 |
 |
このような状況を放置しているならば、組織が壊滅する危険もあるという考えから、全国の指導者は、組合の法的指導機関設置の必要性を訴え、中央会の法制化に向った。
塩澤初代会長と菅谷現会長の両氏が中心となり、全国の協同組合等の代表者と一緒に、強くその実現に努力した。その結果、組合等のより良き指導機関として中央会の法制化が国会でとりあげられ、ようやく昭和三十年七月に成立した。 そして、昭和三十一年一月十八日中央会が誕生したのである。当日、初代会長に塩澤氏、副会長には事業協同組合、企業組合、信用組合の三部会から各々一名が選出された。事業協同組合部会からは菅谷会長が選ばれ、筆頭副会長として初代塩澤会長を助け、代理、代行役として活躍した。そのころ、菅谷会長は事務局に時折り来て、職員に対して昼食をご馳走してくれるなど細かな配慮もしていただいた。 当時の中央会は、会長、副会長といっても非常勤であり、日常事務局に来て業務を指揮監督するというのではない。いいかえると、事務局は運営はすべて常勤の常務理事兼事務局長に一任されていた。 |
|
(二)当時の事務局の実態
その当時の中央会事務局の運営実態は惨憺たるものであった。すなわち補助金に頼りがちで、役所の下請的感覚が横溢していた。「国や東京都から補助金がくるから安心だ」という安易な気持で、指導機関の職員としての自覚や考え方はカケラ程もなかった。当然のことながら計画を立て、これを実行していくような有能な人材はいない。その日を過ごせばまた明日が来る式の烏合の衆(私のその一人)で、指導機関としての機能を全く果たしていなかった。 |
|
|
したがって、財務状態は悪化し中央会自体は日増しに衰退の一途を辿っていた。
格言にある如く、「事業は人なり」といわれるが、団体運営も全く同様で、中央会事務局には真の指導者がいなかったとみるのが妥当である。 初代会長の塩澤氏はこの事態を憂慮し、菅谷会長(当時副会長)に中央会の現状分析の必要性を訴え、この難事を救ってくれるのは、若さと先見性そして決断と実行力のある現菅谷会長をおいて他にいないと判断「菅谷君頼む“やってくれ”」となったわけである。 引受けた菅谷会長は中央会事務局の綿密な調査を行うこと約一ヶ月、塩澤会長に調査の報告書を提出した。 その内容について十数年たって菅谷会長より笑い話で見せていただいた。それを要約すると、財務状態は極めて由々しき状況にあった。すなわち、補助金は順調に交付されていたが、予算化した会費は予定の半分も徴収されておらず、したがって、職員に対する給与は遅配、欠配はまぬがれず、当然のことながら、中央会の取引している業者に対する支払も滞り、加えて全国中央会に納入する負担金は未納のままに放置されていた。 |
 |
|
また、事務局幹部職員の勤務状況は、月の半数以上が、遅刻、早退、欠勤という実情で、一般職員ももちろん、野放しの状態で、勤務時間中外出等の人事管理は一切されておらず、十年来、しみついたままの無規律、無統制という勤務態度であったことなどが、記述されていた。
その報告を受けた塩澤会長は、「これは大変だ!!」このまま放置しておくならば指導機関である中央会は、都下中小企業の信頼を裏切り、全国にその醜態を晒すことになりかねない。 このような現状の中央会を再建するにはこの人以外いないと決断し、菅谷会長宅まで押しかけ再び「菅谷君是非頼む再建を引受けてくれ」と懇請したのである。 |
|
|
|
(三)“菅谷ショック”受けた事務局 |
|
しかし「俺は塩澤会長の命を受けて中央会の再建に来たんだ。辞めるわけにはいかない。辞めるなら職員の君達だ。おれは一人になっても中央会の再建に全力を尽す」と頑張った。 |
|
|
以上、いささか私的な述懐に走ったところもあるが、事務局としてばかりでなく、中央会そのものの立直しも同様である。昔「歴史は夜つくられる」という映画があったが、歴史は人によって作られ、人が歴史を作るものと私は信じている。 |
 |
“専務理事”時代の
|
“中央会から補助金をとり去ったら、タダのサービス企業じゃあないか”
昭和三十六年五月、菅谷会長が再建者として中央会の副会長(専務理事)として就任した時、われわれ事務局職員に対しての第一声が「中央会から補助金をとり去ったら、タダのサービス業である」と。さらに付け加えて「中央会が必要とする費用が全部補助金でまかなえれば良いが、収入の半分は会費である。補助金がないものと仮定すれば、中央会の本質もサービス企業としてとらえられる。要するに会員に喜ばれるサービスを提供して、見返りに会費を頂戴する本質を忘れてはならない」
確かに当時の事務局職員の意識は中央会職員としての自覚に欠けており、組合の設立を中心とした補助金事業の業務をタダ無難に遂行し、その日その日を無計画のままに行動していたといっても過言ではなかった。
このような事務局職員の日常の執務態度は、おのずと会員に対するアフターケア面においても消極的で、会員が来るのを待っているような状態であり、積極的に組合の巡回指導を行うなどはせず、会員とのスキンシップに欠けていた。その結果は、当然のことながら会費の納入状況が悪化し、徴収するのに苦労した。
このような状態をいち早く察知した菅谷会長は、職員の意識革命の必要性を痛感し、中央会事務局職員のあり方についての基本理念をさとしたものである。
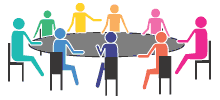 |
“俺は原則人間だ”
菅谷会長は組織を重んじる人である。菅谷会長が、平素口にしている言葉の中に組織論がある。 「組織には、それぞれの目標と使命があり、その組織を運営するのは人であるとともに構成するのも人間である。 したがって、組織には当然のことながら、規律を必要とする。ところが、たまたまその規律を乱し逸脱する不心得な人間が出て来る場合がある。こうした人間をそのまま放置すれば組織はいつのまにか崩壊してしまう。これに対し厳重な注意をし、それでもこりずに同じ行為を二回以上繰り返すことになれば、当然のことながら就業規則に基づいて、始末書を提出させ譴責処分をすることになる。 |
|
それでも反省と理解が出来ない人間は減俸を行い、最終的には辞めていただくことになる。 要するに、原理、原則を理解せず逸脱する人間は、いくら能力があり仕事が出来ても必要としない」というのが不動の信念である。 |
|
|
“事務所(会社)は動物園ではない”
菅谷会長が昭和三十七年に出版した随筆『八方やぶれ経営読本』のなかに事務所(会社)は動物園ではないという項目がある。 その中で特に当時の中央会職員の姿を彷彿させる個所がある。 要約すると次のようだ。 「働くということは人が動くことである、ただ単に動くだけなら動物でもできるが、人間が動くというからには、そこには目的があり、また規則がなければならない。 |
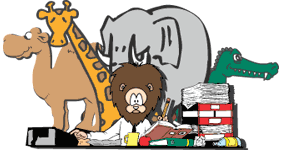 |
| お客を無視しても別に不思議とも無礼とも思わない。事務所が乱雑になっていても平気で歩きまわる。電話が鳴っても無関心で受けようともしない。これでは動物とさして変わらない。動物の動きとは、計画性に乏しく無智で非能率なことをいうのである。 職員の非能率は、そのまま経営に直接ひびく。経営を危うくするようなものに給料を払い、賃上げに応ずるなどということは、経営者として誠に正気の沙汰とは思えない。事務所(会社)も動物園にしてはならない。事務所(会社)が必要なのは人間であって断じて動物ではない」 確かに、当時の職員の勤務態度は無統制、無規律の一語に尽きた。サラリーマンの第一歩である挨拶が出来ない。 朝、黙って入って来、夕方黙って帰る。会長、副会長がたまに見えても「おはようございます」と声を出して挨拶する職員は一人もいない。会釈程度、これでは人間でなく、まさに動物の動く集団でしかなかった。 そこで「挨拶と会釈は違う。挨拶は声を出して『おはようございます』『今日は』『いらっしゃいませ』『さようなら』とするものである。本会においてはまず規律を重んじ、今より挨拶の励行を実行してもらう」と命令した。 以来、職員も完全とはいえないが、挨拶の励行を心がけ実行している。また、仕事の処理の原則としては、その日、その日を無計画にすごすのではなく「計画せよ、実行したら、結果をみよ」と。計画をたててそれを実行に移しても、その結果がプラスだったか、マイナスだったか、その結果をみなければ遊んでいるのと同じだ。そこからは次の計画は生まれてこない。 動物の動きは、常に計画性に乏しく非能率的である。非能率はそのまま経営を危くする。したがって中央会事務所には「計画せよ、実行したら、結果をみよ」と直筆の訓辞を高々と壁に掲示した。また、「組織は一人一人の単独行動ではいけない。新たな事態、問題が生じたときは課として検討し、一課で解決出来ない場合は、他の課と連絡調整を緊密にし、報告連絡を必ず行うこと」としている。このことは三十数年経過した今日でも原点となっている。 |
|
“経営は数字であり結果である” |
このような状況であると、当然財政基盤が弱体化し、会員に対するサービスも低下するので、固定収入源である賦課金の納入状況も悪くなり、じり貧になり、結果的には団体の存在価値も自然に薄れ、終局的には休眠状態に陥いる。
言いかえれば、会員のニーズに対応した事業の推進と、会員とのスキンシップが大切なのである。
“俺には君等を指導する義務がある”
ご存知のとおり菅谷会長は、直接に我々の育成に努めなければならなかった。その時、いわれたことを要約すると。
「人間はとかく他人によく思われたいもので人情に左右されがちである。職場で部下を叱る事も、注意することも出来ない人間がいる。悪く思われたくないから、恨まれたくないから何も言わず見すごして、いい子になっていた方が得だからと思っているのであろう。
家庭や友達とのつきあいであれば、それで良いかもしれないが、組織には目的があり、その目的に向かって職員が一生懸命努力することは当り前のことである。そのためには、職員一人一人が勤勉であり、規律を守り、厳しさを肌に感じて行動をしてもらいたい。
私は、長年原則と信念に基づいて経営を行い、中小企業運動を行って来たが、その経験を通じて得た知識を諸君に伝承していきたいと思う。それが、これから諸君が成長するための礎となり、ひいては組織の強化につながるからである。“順番に行けば、諸君より俺の方が早く死ぬ”したがって、俺のやり方を勉強して置け」
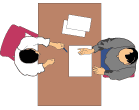 |
“巡回が嫌なら業務命令とする” 中央会の職員は組合を巡回することが基本原則である。このことは政府指定事業にも定められている。ところがその基本原則がなかなか履行出来なかった。 どうして出来なかったのであろうか。それは我々職員が巡回の重要性を理解せず、惰性的に行動していたからで、自ら積極的に行動に移す意欲が皆無であったからではなかろうか。 そこで、菅谷会長は巡回を実行することの重要性を説いた。その内容を要約する。 「事務所に組合の方々が相談に来る。親切丁寧に指導を行うことは、日常の業務として当然で、しかもそれ自体は受け身である。なぜならば、お客がこなければ組合指導の職務を果たすことが出来ないからである。 したがって、本会のように無形のものを売る団体は、こちらから出かけて組合事務局と接触をはかることにより、人間関係を深め、組合の実態を自分の目で確認することが出来る。 また、それが信頼関係を生み、中央会の存在を意識づけることが出来る。その結果、休眠組合等を未然に防ぐことにもなり財政基盤も確立されるのである。 このことが理解出来ない人は、本会の職員としては落第である。したがって、週一回は巡回日と指定することを業務命令とする 」 これが実行され、会員と本会事務局の絆は一層強化されていったことは、いうまでもない。 |
組織には必ずラインとスタッフがいる。せっかく苦心して作った組織であっても、ラインとスタッフが活動しなければ組織は衰退の途を辿る。菅谷会長が再建のためこられた時の中央会事務局は、まさにそのようであった。このことを憂慮した菅谷会長は、組織の機能性と活性化を図るための理念を指導した。
その要旨は−。
「職場の業務体制の基本は、年間の業務計画に対応して編成され、よほどの事情が発生しない限り、変更なく継続されるのが普通で、毎日の業務体制はこの原則に基づいて行動している。具体的にいうと、本会には基本的な業務体制があり、それを職務的に責任分担しているの各課の業務である。各課には毎日決っている仕事の他に、例外的な仕事、時期的な仕事などが錯綜している。したがって、課には、業務を統合するための管理職が必要なのである。管理職はそれぞれの所属する課を統括し、的確に職務を把握して指示をしなければならない。そのために管理職に対して、職務権限と責任を与えている。
しかし、能のない年功序列型の管理職は、、上から何か命令されると、そのまま下に伝える。催促されれば、また、そのまま下に催促する。いわば連絡係にすぎない。本会にはそのような管理職が見受けられるので、これを改めるための心得を指示する」
(基本)
行動の基本は自ら動くことではなく、部下を動かすことにある。
(行動)
一、事務分掌における各課の職責を自覚すること。
二、部下の仕事の内容を、察知すること(毎日決ってある仕事、例外的な仕事、時期的な仕事等)。
三、部下に命令する場合は、その時の情況を考えて事務の流れを阻害しないよう留意すること。
四、他の課との連絡を密にし、上司に対する報告は速やかにすること。
五、常に部下の指導と訓練に心掛け、会の指導理念の徹底を図ること。
“中小企業運動の三原則”
永年にわたり中小企業運動に携った菅谷会長には、中小企業発展のための中小企業運動三原則がある。それを披瀝すると。
「中小企業経営者の会議や集会でいつも叫ばれるのは政治力の結集であり、団結であり、組織の強化であるにもかかわらず、その成果は一向にあがらない。答えは極めて簡単である。しゃべり放し、叫び放しでほとんどが放談会に終っているからである。
大会や会議等で声涙とともに大熱弁を振っていながら、一歩外に出ると利己心で頭の中はゼニ儲けでいっぱいなのである。
団結といい、政治力の結集といい、中小企業運動は共通の目的に向って皆が動くことである。それは『カネ』と『ヒマ』がかかり、そして『しゃべる』ことが必要である。この三つの条件のうちで、『しゃべる』ことに関してはひけをとらない人は大勢いる。
指導者と称される方々の得意中の得意の分野である。したがって、あと二つ、つまり『カネ』と『ヒマ』を出しさえすれば文句がない。ところが、この二つについては大嫌いというのだから、せっかくの政治活動も実がみのらないのが道理である。
全国で六百数十万といわれる中小企業者が一人千円ずつ拠出したら、六十数億円の運動資金が集まる。これだけあったなら、随分中小企業施策について効果的な活動も出来ると思う。誰れかがやるだろうとか、直接自分の儲けに結びつかないものには関心を示さない、というのでは、いつまでたっても中小企業に陽は当らない。この辺で『カネ』だせ、『ヒマ』だせ、『しゃべり』だせ、の順序をはっきり打ち立てる必要がある」
これが中小企業運動の三原則であった。しかし、時代の変化が激しい今日において二十一世紀を展望する時、これからの不透明な時代を乗り切っていくためには、従来の三原則だけではむずかしい。
二十一世紀に向けては、従来の三原則に新しく「知恵」を出し合うことが不可欠であるという確信から一部修正し、「金だせ」「暇だせ」「知恵をだせ」と、本年(六十年)の通常総会で話したことは記憶に新しい。
|
“中小企業にだって労働専門の部署が必要だ” −東京都中小企業経営者協会の創設− 昭和三十年代の労使関係は企業の大小を問わず悪化の途を辿っていた。特に、総評を軸とした労働組合が、中小企業にも積極的に進められてきているのに対し、経営側には労働問題について対応する指導的な役割を果たす機関がなく、そのため労使話合いのルールを定めないまま、争議に追い込まれ、深刻な犠牲を余儀なくされた中小企業は数多くあった。 この事態を憂慮した菅谷会長は、都内中小企業関係団体に呼びかけ、昭和三十四年に東京都中小企業労働問題研究会(現在の東京都中小企業経営者協会=略称「中経協」=)を創設した。それまでも労使協議会の設置が提唱されたことはあったが、労働問題には手をつけるなといった消極性が業界を支配していたが、深刻な中小企業の労働争議に刺激され、ようやく業界の関心が強くなり、それとともに、中小企業関係団体の労働問題に対する意見も一致したのである。 中央会においても労働部門の役割を果たしてもらうため、理事会の決議で中経協を積極的に支援し、また、参画することを決め、同会長には菅谷会長を推したのである。爾来、労使関係の重要性はますます高まり、中経協が設立されてから暫くして、国も中小企業の労働問題の重要性の認識を新たにし、各都道府県中央会に労働専門の労働指導員を配置するようになった。 その後、中経協は中央会と表裏一体となって今日まで、中小企業の労働問題に関する諸事業を展開している。会員の数も現在では五百を超す団体に成長し、関係行政機関からも大企業の「日経連」、中小企業の「中経協」とその存在を高く評価されている。 |
−中小企業組合士制度の創設−
中小企業組合士は、現在全国で二千五十四名の多きを数え、それぞれが全国各地の組合等の事務局で有能な人材として役員、組合員等から全幅の信頼を得ながら誇りと自信をもって活躍している。
この「中小企業組合士制度」を創設した生みの親は、菅谷会長で昭和四十四年である。当時は、来るべき七十年代が激動と変革の時代になるであろうとの予想が強かった。この激動の七十年代を中小企業が組合組織を通じて生き抜いていくためには、組合事業を遂行していく基盤である事務局を強化していくことが必要であり、これを実現させていくためには事務局を支えている役職員の資質の向上を図ることが何よりも肝要であった。
その一方、多数の組合事務局役職員の側から、農協役職員と同様な身分の安定を、早急に確立してほしい旨の要望が、中小企業団体全国団体、その他の会議等で非常に強く叫ばれていた。
しかし、こうした叫び声に対して菅谷会長は「身分の安定を他人に頼むことはナンセンス。むしろ自分自身の力で涵養しなければならない。能力がなくて身分の安定だけ叫んでみたところで、そんなものは砂の上に城をたてるようなものだ。まず自己研鑽に努め、精進と努力によって資質を向上することが先決である」として、中央会が組合事務局役職員に自己研鑽の勉強の場を与えるという人材育成事業を企画したのである。しかも勉強の場の提供だけにとどまらず、勉強の成果を試験し、合格者には「中小企業組合士」の称号を与えるという画期的な資格制度を創設した。
この中小企業組合士制度は、勉強に意欲を出させると同時に自己の身分安定の一つの証につながり、自信と自覚を持たせるところに大きな意義があった。以来「中小企業組合士制度」の着実な実績は、発足当初「士」の称号を与えることに難色を示した中小企業庁も遂に認めるようになった。現在では、毎年制度普及のための予算措置を講ずるなど、国の支援を得、今や全国規模の制度として普及発展し、関係方面からも高く評価されている。
これは、菅谷会長の組合人材育成こそ組織の強化につながり、ひいては中小企業振興に寄与し、しかも、事務局役職員の身分安定の基礎固めになるとの堅い信念の成果である。(筆者は東京都中小企業団体中央会前専務理事)


