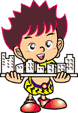 |
||
 |
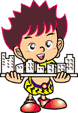 |
||
 |
東京仏壇は、頑なまでに、伝統的な技術と江戸気質を守り続けています。 |
|||||
|
|||||
東京唐木仏壇工業協同組合は、主に台東区、荒川区、足立区の仏壇製造事業者が、唐木材や資材等の共同購買事業を中心に戦前より活動していた任意団体での事業に加え、組合会館の取得、共同販売事業、金融事業等を追加し昭和44年6月に103人のメンバーで協同組合を設立しました。組合設立の翌年昭和45年3月には2階建ての組合会館が完成し、1階は展示場、2階を研修会や総会、理事会が開催できる会議室になっています。 |
|||||
|
|
||||
昭和57年12月に組合員の作品が伝統的な優秀技術であることが認められ、東京都の「東京都伝統工芸品指定産地組合」に指定され組合員の作成した仏壇は‘東京仏壇’として幅広く知られています。 |
|||||
東京仏壇はすべて職人の手づくりによる江戸気質をよく表しており、「くるいがない」「虫がつきにくい」「丈夫」「木目がきれい」を基本に、黒檀、柴壇、桑、欅、花梨、杉、タモ、鉄刀木などの唐木や銘木を使用しており、それぞれの持ち味を生かしているのが特徴です。歴史的には仏壇に唐木材が使用 されるようになったのは、江戸仏師三代目「安田松慶」が嘉永年間の西暦1840年頃からと伝えられております。
|
|
||||
今後の組合の展望として、「組合でホームページを作成し、伝統工芸品‘東京仏壇’の更なるPRに努めたい。又、伝統的な技術を次世代に伝える後継者育成も強化していきます。」と藤波一彦理事長、置栖忠明副理事長、青嶋由雄専務理事からお話しを伺いました。
|
|||||
|
(一口メモ)
|
||||
江戸の伝統工芸品組合シリーズINDEXへ戻る |
|||||
|